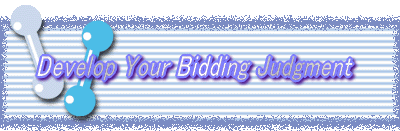
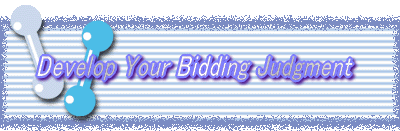
1962年刊行。192ページ。古い本です。
しかし。ここに書かれているビッドの考え方は、「コモンセンス」を養うにはとてもいい本だと思います。
冒頭で、この本ではビッドシステムの適切な使用によって解決できる75%のハンド以外の、残り25%のハンドの取り扱い方について解説するものであると書かれています。
解説の手法は、ちょうど「Play Bridge with Reese」と同じように「over-the-shoulder」という方法で、Reeseの自戦解説風になっており、何をどう考えるべきかということがはっきり分かります。
全体構成は
Part1−Problems in Constructive Bidding
Part2−Doubles--Competitive,Co-operative and Crass
Part3−Tactical Moves
Part4−Making Progress
Part5−Competitive Decisions
Part6−Protective Situations
Part7−An Element of Surprise
となっています。
いくつか紹介します。
Part3「A Practical Illustration」から
チーム戦でNorthのパートナーがディーラー。オポがバル。
私のハンドは、QJ932
_
JT42
8643
Northが1オープン。RHOが1
とオーバーコール。さて、ここでどうビッドすべきか。
選択肢はパス、1、2
の3つ。さて?
まず2はどうか。後に4
まで競り合いになったとき、パートナーがオポの4
に対してディフェンスレスなハンドの場合はうまくいくが、パートナーの
が強かった場合には4
を守った方が良かったという結果になる。
では1はどうか。競り合いのオークションで
を安全に示せるラストチャンスであり、パートナーが
を持っていなければ
フィットを示さず守りに回ればいい。しかし、オポに
で競り合われて高い代で
サポートを示すと、パートナーがあなたのディフェンスのバリューを誤解して4
にダブルをかけてくるかもしれない。
ではパスは。オポはおそらくで競ってくるだろう。そのときに、
で競れるかどうか判断すればいい。
を示せなくなることは重要ではない。
をコントラクトにした方が明らかに多くトリックを稼げる。しかし、他方でパスして代が上がってからは判断も難しくなるかもしれない。
採点: パス・・・10
2・・・8
1・・・4
これがクイズとして出題されたとき、多くのプレイヤーは2に投票した。しかし、その2年後オリンピアードでアメリカ対ブリテインの試合で、
Q8752

J9754
Q32というハンドで、Southのパスからはじまって、パス−パス−1
−1
−1
とビッドして、4
まで競りあがったときSouthは5
とビッド。オポがダブルしてもう一方のオポが5
。でNorthがダブル、オールパス。で、この5
がメークした。Southはパスか2
とビッドしておけば,もっと状況をよく判断できて6
でサクレたのだった。
Part3「A Little Rope」から
ペア戦。ノンバル。パートナーが1オープン。RHOはパス。
私のハンドは、KJ962
_
975
KT862
私は1とレスポンス。LHOパス。Northのパートナーは2
。RHOパス。さて、ここでどうするか。
選択肢は、3、3
、2
、パス。さて?
考慮事項その1:ゲームの可能性は?
のコントラクトでは9〜10トリック取るのが精一杯と考えられる。
のオーバーコールがないということはNorthは
を4枚持っていると考えられる。しかし、分かれ具合とエントリーの具合で
を3回私の方でラフできるとは考えにくい。また、オポは遅かれ早かれ
をリードしてくるだろう。ただ、他方でゲームは可能かもしれない。パートナーの黒いスートのどちらか一方がボイドかシングルトンAであれば。ここで3
とビッドすることはできる。そしてそれは2
や3
よりは良い。
考慮事項その2:戦略的ビッドをする必要があるのか?
より重要な考慮事項である。2をパスしてもなおさらなるチャンスがあるのだから。パートナーの強さの上限は2
ではっきりしている。またオポは9〜10枚の
フィットをしている。でWestの方が疑いなく強いハンドのはず。Eastは1
のときにオーバーコールできたはずなので。したがって私が2
をパスした場合、Westがダブルか2
と言う可能性は極めて高い。それを防ぐために私はここで3
とプリエンプトする必要があるか?
もし、パートナーがx
KQ9x
AQJxxx
Jxといったハンドを持っていれば2
をパートナーはパス。でオポがもし4
までいったら格好のペナルティーチャンスになる。で、もしパートナーが2
の後すぐにダブルしたら、私は3
とテイクアウトできる。またパートナーが2
に自分で3
と言ったら、さらなる3
に私は4
と言える。オポが墓穴をほる可能性、さらにいろいろなケースにわが方がビッドをつなげられる可能性があるのでパスがベターとなる。
採点: パス・・・10
3・・・6
3・・・2
2・・・1
さらなる考察
注意すべきは、でオポがオーバーコールして競ってくる可能性があっても、その分れが悪くてオポはいいコントラクトにならないことが分かっているからパスできるというkとである。もし私の
がxxとかxxxであれば話は違ってくる。
Axxxx
xx
HJx
xxx
こういうハンドであれば、ゲームの可能性もなさそうでレイズする価値もないが戦略的に3というべきハンドということになる。
この原則はプリエンプティブオープンにも適用できる。
(a)xx
AQJTxxx
Txx
x
(b)_
AQ98xxx
T98xx
x
この2つのハンドを比較して、(a)ではできるだけ高くプリエンプティブオープンする必要があるのに対し、(b)は急がず、他のビッドをまず聞く余裕があるということになる。
(^_^)3 フムフム なるほどぉ^^
Part5「The Pressure Call」から
ペア戦。Weバル。パートナーが1でオープン。RHOパス。
私のハンドは、AJ65
KJ864
83
J7
私は1とレスポンス。Westが1
とオーバーコール。North2
、East2
。さて、ここで?
選択肢は、3、2NT、ダブル、パスの4つ。さて?
最初に考えることは、どちらがどういうコントラクトをメークしそうかということである。まず2はダウンする可能性がある。ダブルをかけて100。2NT,3
がメークするなら、2
をプレイさせる方が結果が悪くなるかもしれない。
次にのコントラクトはどうか。もし、ビッドがわが方だけで1
−1
−2
となったのであれば私は2
はパスするだろう。しかし今のビッドはNorthがWestの1
にフリービッドで2
と言っている。しかもバルで。したがって、Northはおそらくミニマムではないハンドで、かつ良い6枚の
を持っているにちがいない。3
がメークするかどうかはフィネスの可否にかかっているかもしれないが、
Jも有効に働きそうでメークする可能性も高そうだ。
2NTはあまり期待できないコントラクトだ。のOLがきてRHOの
Qによって
Aが追い出された後、急いでトリックを取らなければならなくなる。2NTができるカード配置なら3
もメークするが、その逆はあてはまらないからだ。以上、様々なカード配置の場合にどういうコントラクトができそうか考えてみたが、それを踏まえて、さらに戦略的なビッドの可否について見当してみる。
パス:間違いではないし、上手でないパートナーと組んでるラバーなどの今回とは別のセッティングでならあり得る選択肢である。しかし、ペア戦ではこのようなボーダーラインのハンドはもっと競り合わなくてはならない。50点は悪いスコアになる。
2NT:戦略としては正当である。パートナーはまずいと思えば3、3
に戻せる。マイナス面は、オポに3
と競り合う気をなくさせてしまうかもしれないということと、もしあえて3
と競り合ってくるときはオポはカード配置を知ってしまっているということである。
ダブル:私の好みに近い。しかし、自分のハンドでビッドできる限界を超えるまではペナルティーダブルはかけない方がいいという原則を破ることになる。ただ、もしオポがバルなら1ダウンで200点になるので危険ではあるがあり得る選択肢と言える。
3:マイナス面があるとすれば2
をダウンさせられるのに3
がダウンしてしまう場合があることである。しかし、カード配置が悪くて3
がダウンするなら2
は逆にメークする可能性が高い。また3
は2NT以上に競り合いを誘発するというメリットがある。3枚の
を持つオポーネントはパートナーは
シングルトンと見て競り合ってくるかもしれない。そして、オポが3
と競り合ってきたときこそダブルをかけて2ダウンの300点を取るチャンスにもなる。
採点: 3・・・10
2NT・・・6
パス・・・5
ダブル・・・2
さらなる考察
3ビッドは、ディフェンシブなハンドでは競り合いすぎるなという一般原則に反しているように見える。しかし、その原則はハンドがオポーネント側に属している場合に当てはまるものであることに注意する必要がある。たとえば
Tx
QTxxx
Kxx
J9x
こういうハンドで同じような競り合いになった場合、3とビッドしてもオポーネントは
が強くないのですぐにはダブルはかかりにくいので、その心配はない。しかし、あなた方側は点が優勢ではないので、結局オポーネントが最終判断を下すのに助けになるだけである。
などと興味深い記述が次々と続きます^^
 戻る |
 レビュー3へ |
 トップへ |
 次へ |