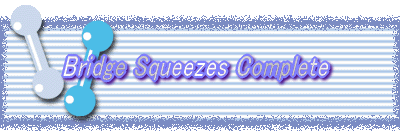
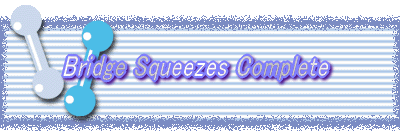
アマゾン書店ではついに品切れでずっと入手できなかったので、アマゾンUSAで古本(used)を注文したら 1週間ほどで届きました(^-^)ニコ なにしろ1959年刊行の古典、手にしたときはちょっと感激しました。
で早速熟読。分類、概念説明の後129の練習問題をもとに説明がさらに続けられていますので、まずシングルダミー問題としてその問題を解いて、その後4人のハンドを見て全体像を理解して、その後説明を読んで行きましたので、時間はかかりました。しかも、回答も懇切丁寧に最後まで解説されているわけではなく、4人のハンドが示されてそれで終わりというのもあって、結局は自分で4人のハンドを見て頭の中でプレーしてみて理解するという形になります。そういうスペースを取る解説部分は当然の前提として基本的に省略されています。ということは、全体で260ページとはいえ、中身的にはその3倍くらいの密度で記述がなされているように感じました。全部解きながら読み進めましたので、ますます時間がかかりました。
内容的には、これまでに読んだどのスクイズ本とも全く異なった角度で分類がなされていて、興味深いですが全体のスクイズの概要がおおむね理解できていないとなかなか難しい本です。
たとえば、概念整理としては、普通は(他の本は)ポジショナルスクイズとオートマチックスクイズに分けて、さらにスクイズカードの反対側に2枚セットの脅し札(Double Menace)(Axなど)があるのが基本的パターンになって、そこからいろいろな発展形が示されていますが、この本では、エントリーの関係で分類したり(シンプルスクイズ)、脅し札の位置関係によって分類したり(ダブルスクイズ、コンパウンドスクイズ)されています。これが、学問的な分類・分類のための分類に過ぎないのか、結果の形からの分類ではないすぐれて実践的な分類なのかはσ(^_^)にはまだ分かりません。
全体構成は
第1章 シンプルスクイズ(40ページ)
第2章 ダブルスクイズ(30ページ)
第3章 エリミネーション(20ページ)
第4章 2スートストリップスクイズ(25ページ)
(サープラス・ストッパースクイズ、バルネラブル・ストッパー
スクイズ、ディレイド・ダックスクイズ)
第5章 トリプルスクイズ(30ページ)
第6章 アドバンスト3スートスクイズ(30ページ)
(ストリップスクイズ、ガードスクイズetc.)
第7章 コンパウンドスクイズ(50ページ)
第8章 トランプスクイズ(10ページ)
となっていて、コンパウンドスクイズについての記述が豊富です(がその部分、まだσ(^_^)には完全には理解し切れていません^^::)
いずれ、全体を整理してまとめたいと思っていますが、ここではとりあえずダブルスクイズの分類について1例を紹介させていただきます。
第2章 ダブルスクイズから
(1)ダブルスクイズの基本パターン
Typ R:RHOの脅し札(R threats)が片側にあって、両サイドの
脅し札(B threats)とLHOの脅し札(L threats)が反対側
にあるパターン。(Kelsey本ではポジショナルダブル
スクイズの基本パターン)
*ダブルスクイズでは脅し札が3スートにあることが
基本で、この本では、その3スートのうち1スート
だけがある側を基点にRとかLとか言っています。
Typ B:両サイド同時の脅し札と R threast,L threatsが別
のサイドにあるパターン。(Kelsey本ではオートマチ
ックダブルスクイズのパターン)
●法則「全てのタイプRダブルスクイズでは、LHOの脅し札に
ついているウィナーは先にキャッシュされなければならな
い。
(これはまぁシンプルスクイズの形を思い浮かべれば
分かると思います^^)
(2)タイプBダブルスクイズの2パターン
Typ B1:B threatsに1枚のウィナーがついているパターン
Ax x
Axx Kx など
Typ B2:B threatsが2枚以上のウィナーがついているパターン
AKx x
AKxx Qx など
*両サイドの脅し札のある反対側にそのスートのウィナ
があるかどうかは区別していないことに注意
●法則(Typ B2)
①「B threatsの反対側にあるエントリーカードにウィナーが
ない場合(AKxx x)、最後のスクイズカードは
B threatsの反対側から出されなければならない」
②「B threatsの反対側にあるエントリーカードにウィナーが
ある場合(AKxx Qx)、それ以外のウィナーをどういう
順番で取ってもOK」
●法則 (Typ B1)
①「B threatsの反対側にあるエントリーカードにウィナーが
ない場合(Ax x)、LHOに対する脅し札には必ず1個の
ウィナーがついていなければならず、かつ、サイドの
ウィナーを取る順はRFLでなければならない」
(F:フリーウィナー。スクイズカードを指す。)
(これをRFLスクイズ呼ぶ。)
②「B threatsの反対側にあるエントリーカードにウィナーが
ある場合(Axx Kx)、RHOに対する脅し札についてい
るウィナーはFウィーナーの前に取らなければならない。
これだけ読んでも、何のことか普通は分からないとは思います。
理論的ですから参考図を見ながら考えて読みすすめればなるほどと分かるのですが、たくさんウィナーがあるスラムハンドのときなんか便利かもしれません^^(タイプRとタイプBでは、ダブルメナスの位置が反対になりますので、RとLの概念が逆転しています。タイプRの場合LHOの脅し札についているウィナーを先にキャッシュすることと、タイプB1の場合のRFLの順、あるいはRHOに対する脅し札についているウィナーは先に取るべしというのは、概念的には ビエナクーの要領ということで この点、Kelsey本ダブルスクイズの22~23ページに分かりやすく解説されています。)
この箇所、Kelsey本では分類の仕方、切り口が全く違っていて、ダブルスクイズの原則は、「ダブルメナス(B threatsのこと)はスクイズカードの反対側になければならない」です。
で、スクイズカードとダブルメナスが同じサイドにあるパターンをインバーテッドスクイズ形と呼んでおり、普通のパターンがスクイズカードを出したときに両方のディフェンダーが同時にスクイズにかかるsimultaneous double squeezeであるのに対し、このインバーテッドのパターンは連続して次々とスクイズにかかっていくseuential double squeezeだと解説しています。で、その後に上記Typ B1に書いてある条件が記述されており、それがポジショナルダブルスクイズとオートマチックダブルスクイズのところでそれぞれ出てきます。
したがって両方読むことによって、ダブルスクイズの様々なパターンが概観できるという感じです(もちろんσ(^_^)にはまだ身についたという実感はありませんが(^^ゞ)。
 戻る |
 レビュー2へ |
 トップへ |
 次へ |