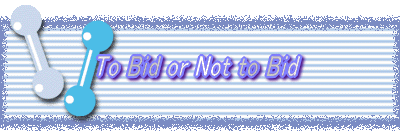
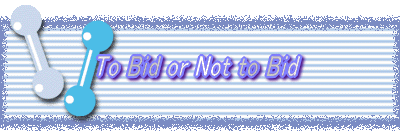
有名な「LOTT」(ローオブトータルトリック)について書かれた本です。
概念自体は何となく知っていましたし、多くのコンベンションにもこの考え方に基づいているものが多いので、分かっていたつもりでしたが、実際読んでみるとなるほどと思うところも多く、やはり百聞は一見にしかずということを実感しました。観戦していても、LOTTがあてはまるケースも多く、観戦これまた勉強の要素がさらに増えたと喜んでいます^^
なお、全体の概要についてはboco_sanのHPの「あなたもLoTTer?」にとても分かりやすく記述されていますので、一読をお薦めします(さらにもう1つは
山田和彦さんのHPの「パーシャル・コントラクトの競り合い」)
全体構成は
第1章 LOTTとはどんなものか
第2章 LOTTの実際の適用
第3章 調整の必要性(頭出し)
第4章 適切なレベルのビッド(含コンベンション)
第5章 適切でないレベルへの押し上げ
第6章 ダブルとLOTT
第7章 ノートランプとLOTT
第8章 (LOTTを踏まえた)格言
第9章 「調整」の全体像
第10章 LOTTに関する他の考慮要素
第11章 世界戦でのLOTTの適用
となっています。
LOTTとは、トータル・トリックの法則というくらいですから、要は、双方の最も長いスーツを切り札にしたと仮定して、その枚数の合計とそのゲームでの合計トリック数はほぼイコールであるというものです。
したがって、ここから
①自分たちの切り札の合計枚数と同じ代まではビッドしても安全である(第4章)。
②オポーネントに、切り札の合計枚数と同じ代でプレーさせないようにすべきである(第5章)。
といった指針が生まれます。
LOTTについて大事なことは、
①競り合いのビッドにおける指針(目安)であること
②双方の合計トリック数の目安であって、自分たちのトリック数とは無関係
であること
③得失表(チャート)をもとに考えることが基本であること
④調整(adjustments)が必要不可欠であること
ということだとσ(^_^)は理解しています。そして、④の調整については、もう1つの著作(「Following the Law」)で詳しく述べられています。
第4章では、LOTTの考え方が背景にあるいくつかのコンベンションの解説がなされています。
(1)バーゲン・レイズ
(2)競り合いでのプリエンプティブ・レイズ
(3)ジャコビー・トランスファー
(4)プリエンプティブ
(5)D.O.N.T
(6)サポートダブル
(7)アンユージュアル1NT
(8)2ウェイ・ドルーリー
第8章 格言では、以下の4点の解説がなされています。
(1)5の代は相手にプレーさせるべし
(2)はっきりしないときは、4Hに4Sとかぶせるべし
(3)ディストリのきついフリークなハンドではっきりしないときは、もう
1回ビッドしてみるべし
(4)オポのトランプを4枚持っているときはペナルティーダブルを考える
べし
第9章では「調整」の仕方、考え方が述べられています。
トータルトリックをトータルトランプ数より少なめに調整する場合
①Negative Purity:オポのトランプスーツのQ,Jなどのマイナーの絵札を
持っているか、あなた自身のトランプスーツのインテリアが貧弱である
場合
②ミスフィット
③フラットハンド(4333、5332など)
トータルトリックを多めに調整する場合
①Positive Purity:上と反対のケース
②ダブルフィット(自分たちも相手方もともにダブルフィットの場合)
③特別の長さやボイドのあるケース
というのが概要です^^
この調整はLOTTの外側にあるのではなくて、LOTTの本質的要素のようです。
第11章では、様々な世界戦でのハンドを題材にあなたならどうビッドするかという質問になっています。ここまで読み進んでくれば、LOTTの考え方もだいたいわかっていますから、この本の冒頭で同じような問いかけがなされていたときに全然分からなくても、ほとんど正解できるようになっているようです^^
たとえば、
問1.(ノンバル)
J754
KT92
A4
T65
YOU LHO P RHO
1S 2C 2S
3C 3S P P
?
問2.(相手方バル)
AK632
62
KQT
Q97
YOU LHO P RHO
P P 3H
3S 4C 4S 5H
?
などです^^(問1は1984年Woman's Teams Olympiad USA、問2は
1979年Bermuda Bowlからです)
 戻る |
 レビュー2へ |
 トップへ |
 次へ |