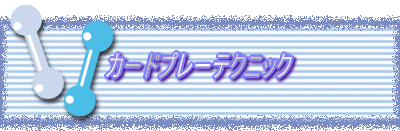
(ブックレビュー詳細)
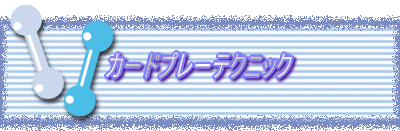
黒川先生の本とならんで σ(^_^)のプレーの基礎を作ってくれた本です。
ネットブリッジに参加して以来、ずっととてもやさしくいつも親切に相手していただき教えてくださったTea_morningさんに薦められて読み始めました
体系立てて書いてあるのですが、ただ単に体系・分類してあるというのではなくて それぞれ 「フィネスとは何か」とか「ラフの本質は何か」とか 基礎の基礎の根っこまでさかのぼって解説されていて、それぞれの技術・テクニックにとって本質的に大事なことが身についたような気がします
しかも、プレーがはじまって13トリック取り終わるまでに起こるいろいろな出来事を プレーヤーが何を考えているかということも含めて書かれていて、かつ そのプレーの過程で注意すべきこと(例 パートナーをフィネスしないように)もついでに触れてあって、とっても実践的です。
章ごとにポイントがまとめてあって練習問題もあります。
すでに4回は読みました。最初は19章のスクイズ以降はよく分かりませんでしたが、繰り返し読むたびに徐々にわかってきました
全体の構成は次の21章構成です。
第1章 ハイカードをプレイしないことについて(ダミープレイ)
第2章 トリックのプロモーション(ディフェンス)
第3章 ラフすべきか否か(ダミープレイ)
第4章 トランプリードとその後(ディフェンス)
第5章 トランプコントロール(ダミープレイ)
第6章 スートコントラクトに対するアタック(ディフェンス)
第7章 ノートランプコントラクト(ダミープレイ)
第8章 ノートランプコントラクトに対するアタック(ディフェンス)
第9章 スートマネジメント(ダミープレイ)
第10章 アタック後の展開(ディフェンス)
第11章 ディフェンダーのカードを読む(ダミープレイ)
第12章 ディクレアラーのカードを読む(ディフェンス)
第13章 セーフティープレイ(ダミープレイ)
第14章 リード、シグナル、ディスカード(ディフェンス)
第15章 エンドプレイ(ダミープレイ)
第16章 エンドプレイを防ぐ(ディフェンス)
第17章 ディフェンダーを惑わす(ダミープレイ)
第18章 ディクレアラーを惑わす(ディフェンス)
第19章 スクイズ(ダミープレイ)
第20章 小さなカードでのディフェンス(ディフェンス)
第21章 トランプを減らすプレイ(ダミープレイ)
さわりの記述をいくつか紹介します。
第1章 ハイカードをプレーしないことについて
「フィネスの本質は「願望」にある。それは、あるカードがどこにあってほしいかと望むことである。じつは、もっと高級なプレーでも根本的に「願望」が同じように存在している。つまり、単純であろうとも高級であろうとも、テクニックというものは、適切なタイミングでの、適切なディフェンダーに対する、適切な願望というものに支えられているのである」(7ページ)
第3章 ラフすべきか否か
「いったい全体ディクレアラーはなぜトランプを集めるのであろうか」(34ページ)
第5章 トランプコントロール
「ラフは、原理・原則ではなく便法である。単にトリックを取るためなのではな く、ほかにはどうしようもないときに、トリックを余分に取るための手段であ る。長いサイドスーツがダミーにあって、そこにトランプもあるというような ときは、そのトランプは、ラフの価値よりは、長いサイドスーツにつなぐ手段 としての価値の方が高いのである。ラフは、それだけでは1トリックの価値だが、エントリーとしては3トリック、4トリックもの価値となる」(72ページ)
読むたびに、常に新しい発見がある本、カードプレーテクニックはそんな本だと思っています。
それから、この本の最後に、訳者の難波田さんがこう書いておられます。「私見であるが、ブリッジというものは、ビッドがある程度基本ができるようになれば、プレイとディフェンスに上達することのほうが、いろいろなビッドのコンベンションを勉強することよりもずっと重要である。ダミーとハンドの両方を見たときに自然にプレイが思い浮かんで、どのようなコントラクトがよいのかが判断できるようにならないと、高級なビッドの勉強をしてもたいして効果がない。プレイとディフェンスの上達にしたがって、ビッドの最大の基本であるハンドの評価能力が向上し、あるコントラクトのためには、パートナーにどのようなアナーがあればよいのか、どのようなディストリビューションであればよいのかを考えられるようになる。このような段階にいたってから、ビッドナリコンベンションなりを勉強した方がよいのである。」と
この文章はσ(^_^)にとって最大の指針になっており、今でもプレー技術上達を最優先に考えていろいろ勉強しているところです^^
 戻る |
 トップへ |
 次へ |